群馬県神流町で、水道水を飲んだ住民14人が下痢や腹痛といった食中毒の症状を訴える事態が発生しました。このニュースに「水道水って安全じゃないの?」「うちの地域は大丈夫?」と不安を感じた方も多いのではないでしょうか。
報道によると、群馬県は2025年4月29日、神流町が供給する水道水が原因の食中毒と断定。
症状を訴えたのは今月11日以降で、複数の患者からカンピロバクターが検出されたとのことです。
幸いなことに入院患者はおらず、全員が快方に向かっているとされていますが、普段私たちが信頼している水道水が原因となったことは非常にショッキングな出来事です。
食中毒の原因「カンピロバクター」とは?私たちの水道水は本当に安全?

事件の経緯:いつ、どこで、何が起こったのか?
- 発生時期:2025年4月11日頃から、住民に下痢や腹痛の症状が出始める。
- 発生場所:群馬県神流町。特に「相原配水池」から供給される水道水を飲用していた住民。
- 被害状況:男女14人(10代未満~80代)が症状を訴える。うち4人からカンピロバクターを検出。入院者なし、全員快方へ。
- 原因物質:カンピロバクター・ジェジュニ
- 原因施設:相原配水池
- 原因とみられるもの:町の調査で、配水池の水が水道法の水質基準に適合していなかったことが判明。保健所の調査では、患者の共通の飲食物は相原配水池から供給された水道水のみ。浄水処理していない水の混入とみられています。具体的には、配水池を消毒した際、浄水処理した水が流入する配管とは別の配管からも水が流入していたことが確認され、町はこの配管を塞いだと報道されています。
- 町の対応:4月19日から水道水の飲用を制限。県は21日から飲用としての供給停止を指導。対象地区住民には飲料水のペットボトルを配布。原因究明と再発防止策を進めている。
カンピロバクターとは?その症状と潜伏期間、感染経路
今回、食中毒の原因とされた「カンピロバクター」。あまり聞き慣れない名前かもしれませんが、実は食中毒の原因菌としては非常にポピュラーなものです。群馬県の発表資料によると、以下のような特徴があります。
- 分布:鶏、牛、ペット、野生動物などの消化管内に生息。
- 主な原因食品:生または加熱不十分な食肉(特に鶏刺し、鶏レバ刺し、焼き鳥など)、二次汚染された食品、飲料水など。
- 主な症状:下痢、腹痛、発熱など。
- 潜伏期間:2~5日(平均2~3日)と比較的長いのが特徴です。
- 予防法:
- 食肉は十分に加熱(中心部を75℃で1分以上)。
- 生肉を取り扱った後の手指、調理器具は十分に洗浄・消毒。
- 生肉はトングや専用の箸で取り扱う。
カンピロバクターは、ごく少量の菌でも食中毒を引き起こすことがあるため注意が必要です。また、感染後にまれに「ギラン・バレー症候群」という神経系の合併症を引き起こすことも知られています。
なぜ水道水から菌が?考えられる原因とは
通常、日本の水道水は水道法に基づき厳格な水質基準が定められ、塩素消毒などにより安全性が確保されています。では、なぜ今回のような事態が発生したのでしょうか?
報道や群馬県の発表によると、神流町のケースでは「相原配水池」の水が水道法の水質基準に適合していなかったこと、そして「浄水処理していない水の混入」が原因とみられています。具体的には、配水池の消毒作業中に、本来接続されるべきではない配管から未処理の水が混入した可能性が指摘されています。これは、何らかの管理体制の不備や、設備のトラブルがあったことを示唆しています。
読者コメントの中には、次のような声も見られました。
「湧水や井戸水ならともかく、滅菌処理を施した水道水にカンピロバクターとはあってはならない事。町の水道事業者の怠慢そのもの。」
(TBS NEWS DIG 読者コメントより要約)
「写真を見る限り、山間の小規模な簡易水道でしょう。…きめ細かいメンテナンスや監理はなかなか難しい現状。水道事業は昔から独立採算制が原則で、収入が少なければ人も維持管理費も建設費も縮小せざるを得ないのです。」
(TBS NEWS DIG 読者コメントより要約)
これらのコメントは、今回の事件が単なる一時的なミスだけでなく、より根深い問題を含んでいる可能性を示しています。
「うちの水道水は大丈夫?」読者の疑問に答えます
今回のニュースを受けて、「自分の住んでいる地域の水道水は安全なのか?」と心配になった方もいらっしゃるでしょう。ここでは、皆さんの疑問や不安に少しでもお答えできればと思います。
もしや食中毒?こんな症状が出たら要注意!
カンピロバクター食中毒の主な症状は、下痢、腹痛、発熱です。
潜伏期間が2~5日とやや長いため、原因が特定しにくいこともあります。
「最近、生焼けの鶏肉を食べたかな?」「水道水を飲んでから体調が…」など、少しでも気になることがあれば、早めに医療機関を受診しましょう。
特に、小さなお子さんや高齢者、免疫力が低下している方は重症化しやすい傾向があるため注意が必要です。
家庭でできる水道水の安全対策とは?
日本の水道水は基本的に安全性が高いですが、それでも不安を感じる場合や、今回のような報道があった際には、以下のような対策を検討してみましょう。
- 煮沸する:最も簡単で確実な方法は、水道水を沸騰させることです。カンピロバクターなどの細菌は熱に弱いため、1分以上沸騰させれば死滅します。
- 浄水器を利用する:浄水器の種類によっては、細菌や塩素などを除去できるものもあります。ただし、フィルターの性能やメンテナンス状況によって効果が変わるため、説明書をよく読み、適切に使用することが大切です。カンピロバクターのような細菌を完全に除去できるかは製品によりますので、過信は禁物です。
- 自治体の情報を確認する:多くの自治体では、水道水の水質検査結果をホームページなどで公開しています。自分の住む地域の水質情報を定期的にチェックするのも良いでしょう。
- 異常を感じたら連絡:水道水の色がおかしい、異臭がする、味が変だと感じたら、すぐに飲用を中止し、お住まいの自治体の水道局や保健所に連絡しましょう。
「カンピロバクターとは?」で触れたように、食肉からの感染も多いため、調理時の衛生管理も徹底しましょう。
背景にある構造的問題:他人事ではない水道インフラの危機
今回の神流町の水道水食中毒事件は、単に一つの自治体の問題として片付けられるものではないかもしれません。読者コメントにも多く見られたように、日本の水道インフラが抱える様々な課題が背景にある可能性が指摘されています。
忍び寄る水道インフラの老朽化と管理の課題
日本の水道管の多くは高度経済成長期に整備されたもので、法定耐用年数(40年)を超過しているものが全国的に増加しています。老朽化した水道管は、漏水のリスクだけでなく、水質悪化の原因となることもあります。
「水道インフラの老朽化と管理不足が原因で、安全な水の供給が難しくなっていると感じています」
(テレビ朝日 NEWS 読者コメントより要約)
「日本全国法律上塩素0.1ppm以上0.4ppm以下と決まっているので、安心して飲めるはずですが水道管の耐久年数40年を超えた物が多く腐食も増えているはずです。…いずれ日本も水道水を生で飲めない時代が来ますし断水も頻繁に起こるでしょうね。」
(TBS NEWS DIG 読者コメントより要約)
これらの声は、インフラ維持の難しさを物語っています。
地方自治体が抱える厳しい現実
特に神流町のような山間部の小規模な自治体では、人口減少や高齢化が進み、水道事業を維持するための財源や専門的な知識を持つ人材の確保が難しくなっているという指摘もあります。
「この自治体はかなりの過疎地です。…山岳過疎自治体であり、管理のための予算や人手が足りないのでは、と想像します。このような自治体は日本には山のようにあると思います。こういった寒村、過疎自治体からインフラ整備ができなくなると予想します。」
(テレビ朝日 NEWS 読者コメントより要約)
相原配水池から水道水の供給を受けるのは25世帯とのこと。限られた利用者で広範囲なインフラを維持していくことの困難さが伺えます。
水道事業の民営化と外資参入への懸念の声も
一部の読者コメントでは、水道事業の民営化や外国企業の参入が、将来的に日本の水道水の安全性に影響を与えるのではないかという懸念も表明されています。
「こう言う生活に無くてはならない所に中国や海外企業が参入、買収してきてる。日本の安全が脅かされる。…国はしっかりと安全基準などを徹底してくれ」
(テレビ朝日 NEWS 読者コメントより要約)
今回の神流町のケースと直接関連があるかは不明ですが、水道という重要なライフラインのあり方について、国民的な議論が必要とされているのかもしれません。
今後の対策と私たちにできること
神流町の現在の対応と今後の見通し
神流町では、問題が確認された配管を塞ぎ、配水池の消毒作業を行いました。
その後、細菌数などは基準値に収まったと報告されています。今後はカンピロバクターの検査を行い、飲用の可否を判断するとしています。
被害に遭われた方々へのケアと共に、原因究明と再発防止策の徹底が求められます。
水の安全を守るために、私たち一人ひとりができること
「安全な水」は当たり前ではありません。今回の事件を教訓に、私たち一人ひとりができることもあります。
- 関心を持つ:自分の住む地域の水道事業や水質に関心を持ち、情報を集めましょう。
- 異常を報告する:水道水に異常を感じたら、放置せずに自治体や保健所に相談することが大切です。(家庭でできる水道水の安全対策とは?も参照)
- 節水を心がける:限りある資源である水を大切に使うことは、インフラへの負荷軽減にも繋がります。
- 防災意識を持つ:災害時などには断水や水質悪化のリスクも高まります。普段から飲料水の備蓄を心がけましょう。
まとめ:安全な水を未来へつなぐために
群馬県神流町で起きた水道水による食中毒事件は、私たちにとって「水と安全」について改めて考えるきっかけを与えてくれました。
被害に遭われた方々の一日も早い回復を願うとともに、このような事故が二度と繰り返されないよう、行政による徹底した原因究明と対策、そして私たち自身の意識改革が求められています。
蛇口をひねれば安全な水が出てくる社会。
この恵まれた環境を守り、未来へつないでいくために、私たち一人ひとりができることを考え、行動していくことが重要です。
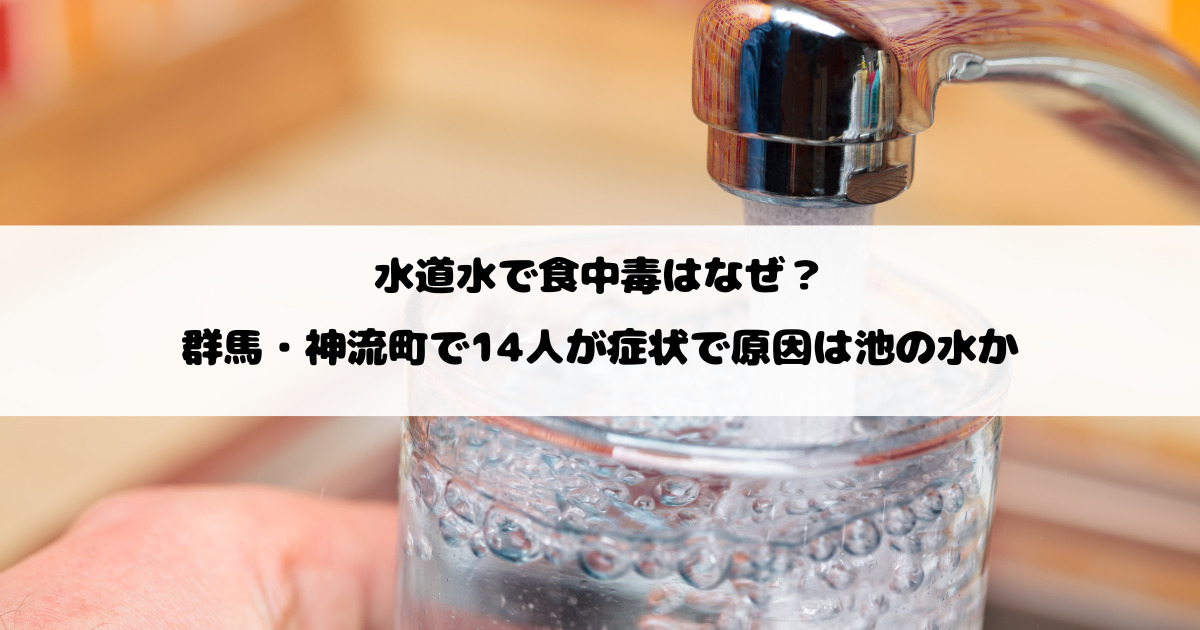

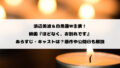
コメント