かつて日本の百貨店や家電量販店を席巻した中国人観光客による「爆買い」。
その光景が、今は昔の話となりつつあります。
2025年現在、訪日中国人旅行者の数はコロナ禍以前の水準に回復、むしろ増加傾向にあるにもかかわらず、高額品の売上は伸び悩んでいます。
一体なぜ、あれほどすさまじかった爆買いは消えてしまったのでしょうか?
本記事では、その理由と背景をデータや現地情報から徹底的に分析し、今後のインバウンド市場がどう変化していくのかを考察します。
爆買い終了の号砲!円高とブランド値上げの「お得感」消失
結論から言えば、爆買いが終焉した最大の直接的要因は「金銭的なうまみがなくなった」ことです。
2023年から2024年春にかけて、1元=22円台に迫る歴史的な円安が「爆買い」を再燃させました。当時、ルイ・ヴィトンやプラダといった高級ブランド品は、日本の免税店で買うと中国国内より3割も安く手に入り、「飛行機代やホテル代を入れても元が取れる」と考える中間層が殺到しました。
しかし、その状況は2025年に入り一変します。
- 為替の円高転換
2025年に入り為替が円高に振れたことで、円安による価格メリットが大きく薄れました。 - 相次ぐブランド品の値上げ
LVMH(ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー)グループなどは、他国との価格バランスを取るため2023年から日本国内で複数回の値上げを実施。円安進行中はそれでも日本が割安でしたが、円高転換と度重なる値上げが重なり、他国との価格差は一気に縮小しました。
この「円高」と「値上げ」のダブルパンチにより、わざわざ日本で高級ブランド品を買う「お得感」が消失。
これが、百貨店の免税売上高が失速する直接的な引き金となったのです。
中国経済の失速と消費スタイルの構造的変化
爆買いの失速は、為替だけの問題ではありません。
より根深い要因として、中国国内の経済状況と消費者の意識変化が挙げられます。
2023年頃から中国経済の変調は指摘されていましたが、多くの国民が不景気を本格的に体感し始めたのは2024年後半からと言われています。
失業者の増加やボーナスカットが現実味を帯びる中で、消費行動はより慎重な「理性的消費」へとシフトしています。
これは、複数のプラットフォームを比較して最も安く、コストパフォーマンスが高いものを求める消費スタイルのことです。
さらに、コロナ禍で急成長した「越境EC(電子商取引)」の存在も無視できません。
アリババグループの幹部が指摘するように、かつての爆買いは「日本でしか買えないもの」が多かった時代だからこそ起きた現象でした。
今や日本の人気商品はオンラインで手軽に購入できるため、旅行中に大量に買い込む必要性が低下したのです。
つまり、中国国内の経済不安と買い物手段の多様化が、日本での消費行動を「特別な爆買い」から「日常の延長線上にある賢い買い物」へと変化させたと言えるでしょう。
誤解だらけの爆買い神話。主役は富裕層ではなく「中間層」だった
「爆買いが消えた=中国人富裕層が日本から離れた」と考えるのは早計です。実は、2024年頃に高級ブランド店に押し寄せた客層の多くは、本当の富裕層ではなく「中間層」でした。
彼らの目的は、円安を利用して「お得にブランド品を手に入れること」であり、中には友人から購入を頼まれたり、転売目的で購入したりするケースも少なくありませんでした。
彼らはまさに「理性的消費」を実践し、コストパフォーマンスを重視して海を越えてきていたのです。
一方で、真の富裕層は、価格差だけを理由に旅行先を決めることは少ないとされています。彼らの関心は、よりユニークな体験や、そこでしか得られない価値へと向かっています。
爆買いの主役が「コスパを重視する中間層」であったという事実を理解することが、現在のインバウンド市場を正確に捉える鍵となります。彼らが価格メリットの薄れた高額品から離れるのは、ごく自然な流れなのです。
「コト消費」へのシフトは本物か?今後のインバウンド戦略の鍵
百貨店での高額品消費は落ち込みましたが、中国人観光客の消費がすべて消えたわけではありません。
ドラッグストアやドン・キホーテなどでの日用品や化粧品の売上は依然として好調であり、2025年4〜6月の中国人観光客1人あたりの買い物額は、他国からの観光客を圧倒しています。
これは、彼らの消費の対象が「高級ブランド品」から「品質の高い日本の日用品」や「体験(コト消費)」へとシフトしていることを示唆しています。
今後のインバウンド戦略で重要になるのは、中国人観光客を「爆買いする集団」としてひとくくりに見るのではなく、セグメント分けしてアプローチすることです。
- 富裕層向け: プライベートな文化体験、オーダーメイドのツアーなど、高付加価値な「コト消費」を提供。
- 中間層・リピーター向け: 地方の魅力や特定の趣味(アニメ、食、アウトドアなど)を深掘りするコンテンツを強化。
目先の売上に一喜一憂するのではなく、日本の文化やコンテンツそのものに関心を持つ層と真摯に向き合い、持続可能な関係を築くことこそが、今後の日本の観光立国に求められる戦略と言えるでしょう。
ただし、どのような層をターゲットにするべきか、またオーバーツーリズムとのバランスをどう取るかについては、今後も継続的な議論が必要です。
まとめ
中国人観光客による「爆買い」が消えたのは、以下の複合的な要因によるものです。
- 円高とブランド品値上げによる「お得感」の消失
- 中国国内の景気低迷と「理性的消費」へのシフト
- 爆買いの主役が富裕層ではなく「中間層」だったという実態
- 越境ECの普及と旅行スタイルの変化(モノ→コトへ)
かつての熱狂的な爆買いは、円安などの複数の要因が重なった一過性の現象でした。
これからのインバウンド市場は、単価の高いモノを大量に売るモデルから、日本の多様な魅力を体験してもらい、継続的に訪れてもらう「質の高い関係性」を築くモデルへの転換が不可欠です。
爆買いの終焉は、日本のインバウンド戦略が新たなステージへ移行する号砲なのかもしれません。
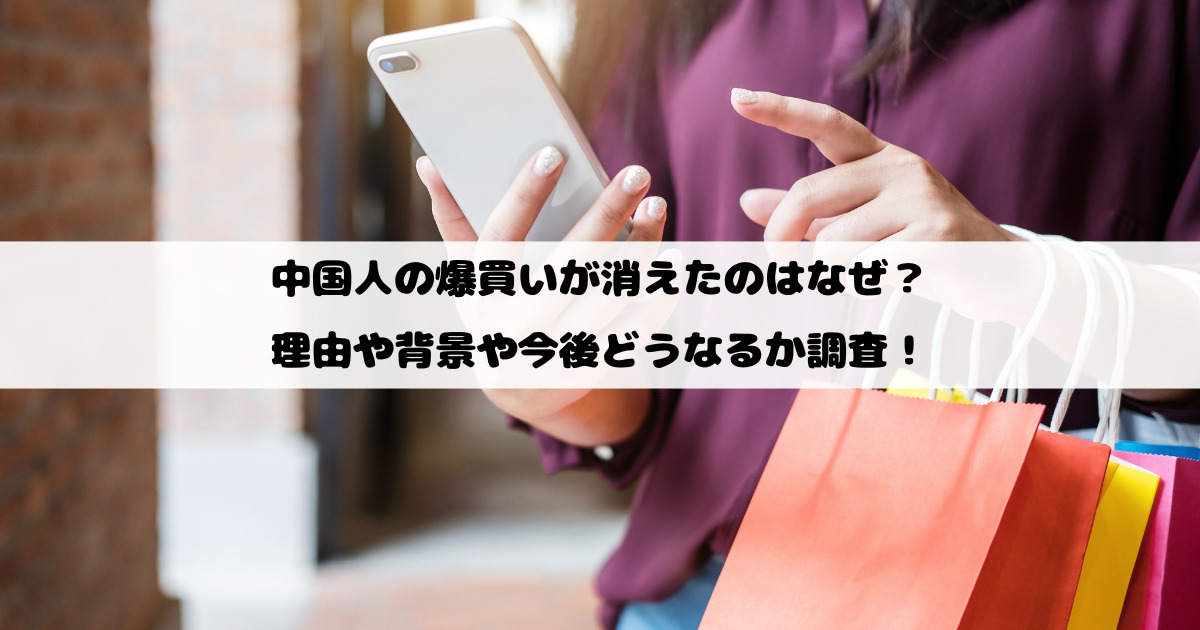


コメント