総合商社の雄、三菱商事が国内3海域の洋上風力発電事業から全面撤退するという衝撃的なニュースが飛び込んできました。
原発1.7基分に相当するこの巨大プロジェクトは、日本のクリーンエネルギー政策の柱と期待されていただけに、その影響は計り知れません。
「なぜ今になって撤退するのか?」「もともと無理な計画だったのでは?」「日本のエネルギー政策は大丈夫なのか?」多くの人が抱くであろうこれらの疑問に、本記事では深く切り込んで解説します。
【理由】なぜ撤退?直接の引き金は「想定外のコスト高騰」
三菱商事が撤退を決断した直接的な理由は、「物価高と円安による建設コストの急激な高騰」です。
2021年の計画策定時とは異なり、ウクライナ危機以降、世界中で鋼材などの資材価格が1.5〜2倍に跳ね上がりました。
さらに歴史的な円安が追い打ちをかけ、海外から調達するタービンなどの重要部材のコストも想定をはるかに超える水準に達しました。
企業が事業計画を立てる際、ある程度のコスト上昇は織り込んでいますが、今回の上昇幅はそれを遥かに超える「想定外」のものでした。
このまま事業を進めても巨額の赤字を垂れ流すことは確実と判断し、約200億円とも言われる違約金(預託金没収)を支払ってでも撤退する方が合理的、という苦渋の経営判断に至ったのです。
【背景】そもそも無理があった?「安すぎる落札価格」という時限爆弾
しかし、この問題の本質は単なるコスト高騰だけではありません。
より根深い原因は、2021年の公募時に三菱商事連合が提示した「異常なまでに安い売電価格」にありました。
当時、三菱商事連合は1kWhあたり11.99~16.49円という価格を提示し、競合他社の半額から3分の2程度の安値で3海域全ての事業権を独占しました。
業界では「価格破壊」と衝撃が走り、当時から「本当にこの価格で採算が取れるのか?」と疑問視する声が絶えませんでした。
この「安値受注」は、コスト上昇に対する耐性を全く持たない、極めて脆弱な事業計画だったと言えます。
いわば、いつ爆発してもおかしくない時限爆弾を自ら抱え込むようなものでした。
結果的に、その爆弾が世界的なインフレという導火線によって爆発し、計画そのものが破綻したのです。
【影響】誰が困る?地元経済への大打撃とエネルギー政策の停滞
今回の撤退劇は、三菱商事が損失を被るだけで済む話ではありません。
その影響は国全体、そして地元経済に深刻な爪痕を残します。
- 地元経済への致命的な打撃
事業予定地だった秋田県などでは、この巨大プロジェクトを見越して地元経済が大きく動いていました。作業員向けのホテルが新設され、地元高校では洋上風力関連の技術者を育成するための学科新設まで決まっていたのです。これらの先行投資は全て無駄になり、期待されていた雇用も消滅。地元関係者にとっては「無責任すぎる」では済まされない、人生を揺るがす裏切り行為に他なりません。 - 国のエネルギー安全保障の崩壊
原発1.7基分に相当する電力供給源が白紙になったことで、日本のエネルギー政策は大幅な見直しを迫られます。再公募するにしても、一度頓挫した案件に手を挙げる企業が現れるかは不透明であり、計画は数年以上遅れることが確実です。これは、脱炭素目標の達成を遠のかせるだけでなく、日本のエネルギー安全保障そのものを脅かす事態と言えるでしょう。
【今後】日本の再エネはどこへ向かう?問われる国の制度設計
この失敗を「三菱商事の経営判断ミス」と片付けてはいけません。
多くの専門家が指摘するのは、価格の安さだけで事業者を選定する「国の入札制度そのものの欠陥」です。
事業の実現可能性や技術力、財務の健全性などを十分に評価せず、安さだけで落札させてしまう現行制度が、今回の事態を招いた根本原因の一つです。
極端な安値での入札がまかり通れば、今後も同様の事態が繰り返される危険性があります。
また、台風が頻繁に襲来し、遠浅の海が少ないという日本の地理的条件が、そもそも大規模な洋上風力発電に向いているのかという根本的な議論も必要です。
太陽光発電は環境破壊、地熱発電は規制の壁など、他の再生可能エネルギーも課題を抱える中、日本のエネルギー政策は大きな岐路に立たされています。
まとめ
三菱商事の洋上風力発電事業からの撤退は、世界的なコスト高騰が引き金となりましたが、その根本には「安すぎる無謀な入札価格」と「価格偏重の国の制度設計」という構造的な問題が存在します。
この一件は、地元経済に深刻なダメージを与え、日本のエネルギー政策を大きく後退させました。
この失敗を教訓とし、国は事業の実現可能性を重視した制度へと見直し、より現実的で持続可能なエネルギー戦略を再構築することが急務です。
この問題の今後の動向を、我々は厳しく注視していく必要があります。
▼あわせて読みたい
三菱商事の洋上風力撤退でどうなる?地元経済、電気代、日本のエネルギーの未来を徹底予測!
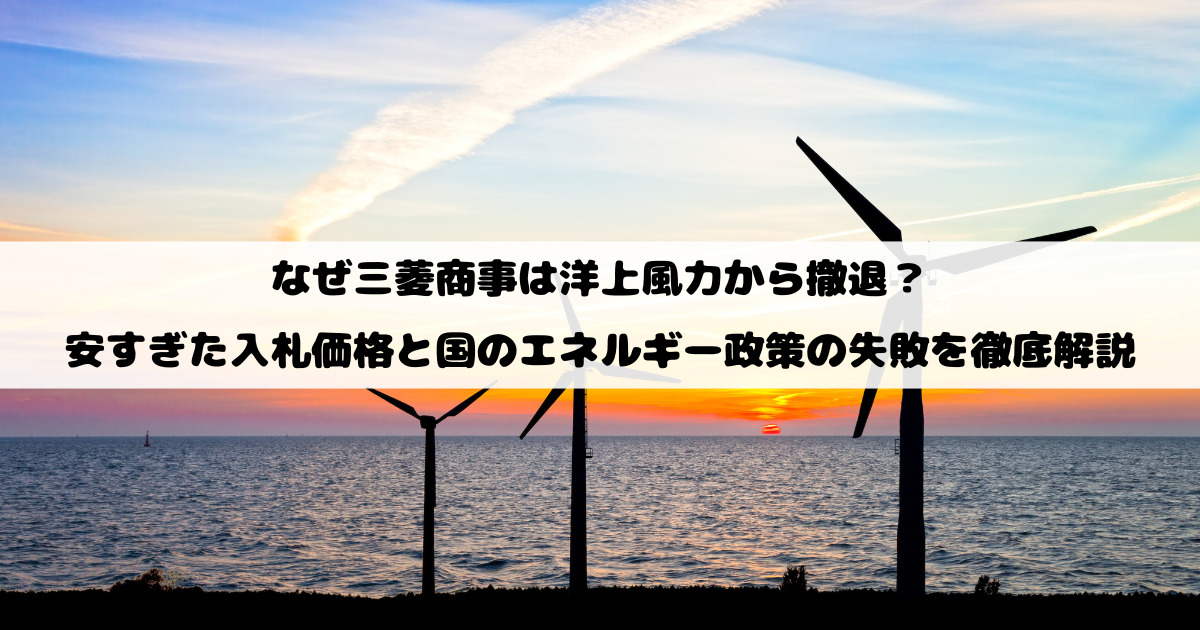


コメント